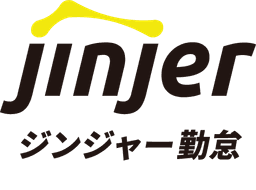昨今、派遣社員という働き方も社会に定着しています。柔軟な労働力の確保、専門スキルの即戦力化、コスト削減などの目的で、特にプロジェクトベースのタスクや季節変動のある業務で重宝されています。その一方で派遣元企業と派遣先企業の双方で勤怠状況の把握が困難、管理や手続きが煩雑化するなど、雇用形態が特殊・複雑であることに由来する課題も挙がります。
この記事では派遣社員の勤怠管理について、派遣元と派遣先それぞれの視点で課題と解決策を示します。派遣元、派遣先それぞれの役割とニーズの違いを理解することで、派遣社員の勤怠管理を効率化するポイント、課題を解決する方法が明確になるでしょう。併せてこの課題解決に向けた、派遣社員の勤怠管理にも需要の多いおすすめの勤怠管理システム11製品を紹介します。
派遣社員の勤怠管理「勤怠管理システム」おすすめ製品一覧
目次
派遣社員の勤怠管理における課題
まずは派遣社員の勤怠管理における代表的な課題を確認しましょう。まず、派遣先企業と派遣元企業、そのどちらも派遣社員に関わる勤怠管理に一定の責任を持ち、その管理・把握すべき項目、役割にいくつかの違いがあります。また派遣先ごとに異なる労働条件やシフト体制があるシーンも一般的です。その分、実労働時間を正確に把握するのが難しくなります。
派遣先と派遣元で役割と責任分担が異なる
派遣元企業は派遣社員の雇用主として、給与計算・支払い、社会保険の手続き、有給休暇の付与管理、就業規則の明示などの重要な労務管理を担います。
一方の派遣先企業は実際の職場監督・管理を担います。派遣社員と直接的な雇用契約はないものの、派遣社員の日々の業務指示や労働時間の管理、休日等取得の管理、安全衛生面や職場環境の確保といった実務における適切な管理が求められます。
このように両者(社)で管理すべき項目や責任が分かれているため「自社だけ大丈夫ならばいい」とはなりません。連携がうまくされていないと手続きの重複や漏れが発生しやすく、何より派遣社員への労働環境や賃金、サポート体制に影響が及ぶ可能性があります。
労働時間の把握が難しい
派遣に伴う契約内容は人材の能力や求める内容、派遣先企業の就業ルールやシフトなどによって多様化します。日々の残業や休日出勤が不規則に発生する場合もあります。そのため、派遣元企業が派遣社員の正確な勤怠情報を得るには、定期的かつリアルタイムな情報確認と共有が求められます。
しかしシステムが整っていないとタイムカードのような紙ベース、エクセルやメールのような手入力ベースの管理に頼らざるを得ず、サービス残業の見逃しや給与計算のミス、法令違反に気が付かないといった問題に発展するリスクが多分に残ります。
そのため、派遣社員を人材として有効に活用し、また派遣社員が安心して勤務できるよう、派遣先/派遣元それぞれで対策することが求められます。具体的には勤怠とその関連情報を“データとして正しく、リアルタイムに一元管理”する勤怠管理システムのようなITシステムの導入が勧められます。
おすすめ“多様な働き方”を実現したい企業に向く勤怠管理システムの選定基準
派遣元と派遣先それぞれの勤怠管理項目
派遣社員の勤怠管理においては、派遣元企業と派遣先企業で管理すべき項目が異なります。それぞれの視点から押さえるべきポイントをまとめます。
派遣社員の労務管理は、雇用主である派遣元企業の義務と実務監督を行う派遣先企業の責務が両輪となって進めます。給与計算や有給休暇の付与などは派遣元企業が正確に対応する必要があり、現場でのシフト管理や職場環境の整備は派遣先企業が担うことになります。これらを混同しないよう明確に区分しながら、適切に連携を行うことが円滑な勤怠管理の鍵となります。
派遣元企業の管理項目
- 給与計算と支払い、36協定の締結
- 複数派遣先管理を踏まえた労働時間管理
- 有給休暇の適正管理
- 派遣先管理台帳の管理
派遣元企業は、労働条件通知書の作成や給与計算、社会保険の手続きなど、派遣社員の雇用主としての責任を負います。派遣社員は自社(派遣元)の就業規則とともに派遣先の規則も踏まえる必要があります。そのため派遣元企業は、複数の派遣先で働く派遣社員の労働時間を一元的に管理することが難しくなる点が課題です。勤怠管理システムを活用し、派遣先からの労働実績データをスムーズに取り込む仕組みが不可欠となります。
給与計算と支払い、36協定の締結
派遣元企業は労働基準法に従った給与計算を行い、支払日までに正確な金額を支払うことが法律上の義務です。また時間外労働を行う場合には36協定の締結が必要となり、合意内容を踏まえた労働時間の上限管理が求められます。これらのプロセスを適切に行うためには、勤怠情報がリアルタイムで把握できる仕組みが欠かせません。
36協定(サブロクきょうてい)とは、労働基準法第36条に基づく労使協定(時間外・休日労働に関する協定書)のことです。労働基準法第36条で、時間外労働や休日労働を認めるためには労使双方が協定を結び、労働基準監督署に届け出る必要があると規定されています。この協定は労働者が法定労働時間を超える時間外労働や休日労働を行う際に向け、労働者(派遣社員の)代表と使用者(派遣元企業)との間で結びます。36協定を締結しない残業等(法定労働時間を超える労働および法定休日にさせた労働など)は違法となります。
複数派遣先管理を踏まえた労働時間管理
派遣社員が複数の派遣先で就業するケースもあります。派遣元企業はこの合計労働時間が法定範囲を超えないよう管理する必要もあります。各派遣先での管理方法はバラバラかもしれません。しかし合計勤務時間を把握できなければ、36協定に反してしまう法的リスクが生じます。システムで一元管理し常に正確なデータをもとに労働時間の調整ができるよう仕組みを整えることが大切です。
有給休暇の適正管理
従業員は労働基準法に定められた有給休暇日数が付与される権利があり、当然それは派遣社員も同じです。派遣元企業は派遣先での勤務実績や通算勤務期間を踏まえて休暇を計算し、取得状況を管理する必要があります。派遣社員のモチベーション低下やトラブルの原因になることから、適正な付与と管理、慎重な運用が求められます。
派遣先管理台帳の管理
派遣先管理台帳は、派遣先企業の情報と派遣社員の情報──就業条件や契約内容、履歴、条件などを記録するもので、法令で作成が義務付けられています。管理台帳を適切に運用し、派遣元企業と必要な情報共有を行うことでスムーズな勤怠管理が可能となります。
派遣先企業の管理項目
- 労働時間管理と安全衛生確保
- 有給休暇の把握と公正な待遇確保
- 勤怠データの連携と報告
派遣先企業は派遣社員に対して、業務指示や勤務スケジュール、残業の管理など実務上範囲の管理を行います。これには派遣社員が働く職場環境の安全衛生管理なども含まれ、就業中のリスクを最小化することが求められます。これらの職場運営に密着した管理項目を明確にし、派遣元企業との情報共有をしっかり行うことが適切な勤怠管理の前提となります。
労働時間管理と安全衛生確保
派遣先企業は日々のシフト組みや残業確認などを通じて、派遣社員が無理なく働ける環境を整えます。作業内容や就業時間が長引く場合においても同様で、また安全対策や休憩時間の確保も不可欠です。派遣社員が安心して従事できる環境づくりは自社の生産性の向上にもつながります。
有給休暇の把握と公正な待遇確保
派遣社員にも、派遣先企業の社員・従業員と同様に労働環境、有給休暇を取得できる機会を保証・提供することが重要です。有給休暇は派遣元と連携を図りながら取得促進を行うことが求められます。適切な休暇管理や待遇の確保は、派遣社員との信頼関係を深めることにつながります。
勤怠データの連携と報告
派遣社員の勤怠データを双方で正しく管理するために、派遣元企業とのシステム/データ連携の体制も求められます。勤怠データをリアルタイム/自動的に連携する機能・体制を備えることで、派遣元企業との情報共有が円滑になり、データの二重入力や手動での人的ミスなどを防ぎます。法定労働時間を超える場合や異常がある場合にアラートを発する機能があれば、迅速な対応が求められる状況にも対応できます。
また、月次や週次のレポートが自動生成されれば派遣元企業への報告も容易になります。
派遣社員の勤怠管理に向けた勤怠管理システムの要件
では派遣元、派遣先のそれぞれで、派遣社員の勤怠管理を効率化するためのシステムにどのような機能があるとよいかを確認しましょう。特に求められるシーンが多い機能は以下の通りです。
- 基本勤怠管理機能
- 派遣元企業向けの管理機能
- 派遣先企業向けの管理機能
- モバイル対応機能
- 申請ワークフロー機能
- データ連携機能
基本勤怠管理機能
勤怠管理システムには、始業・終業時刻、休憩時間の打刻、残業時間の算出、休暇・休業管理、勤怠データの集計・分析・レポート化機能、人事・給与情報/システムとの連携機能などが基本機能として備わります。
これらの機能そのものは、勤怠管理システムとうたうものならばほぼ全ての製品に備わります。しかし「それが全て自社のニーズと合っている」とは限りません。会社の規模や業態・業種、自社特有のニーズ、管理人数などで異なることでしょう。また多くの場合、ニーズや解決したい課題は「派遣社員の勤怠管理だけ」というよりは、「“自社全体の”勤怠管理の課題解決」になるでしょう。
このため製品選びの第一歩は、さまざまな視点でできるだけ多くの課題を拾い上げて考察することになります。別部署や管理部門、現場、経営層・上層部なども遠慮なく巻き込みながら要件を詰めていく作業を進めていくとよいでしょう。この上で、派遣社員の勤怠管理、派遣元/派遣先としての機能の有無や効果を追加考察していきましょう。
なお、派遣社員による勤怠の打刻は、派遣元企業のシステムで行う場合と派遣先のシステムで行う場合が考えられますが、一般的には派遣先企業のシステムで行い、派遣元とデータを連携することが多いです。両社目線では、結果として「双方で管理する」となります。
派遣元企業向けの管理機能
派遣元企業には、複数の派遣先から集まる勤怠情報を一元的に把握・管理し、複数の派遣先とのデータ連携を適切に行う体制が必要です。給与計算や社会保険、マイナンバー管理のようなタスクも含めて連携したり、自動化したりできる機能も求められるでしょう。労働時間が一定基準を超える場合にアラートを出すなど、36協定違反を未然に防ぐ仕組みもあるととても有効です。
派遣先企業向けの管理機能
派遣先企業には、シフト作成・管理や出退勤管理といった日常の勤怠管理に加え、安全衛生面や休暇・休憩時間の実績把握、派遣元企業と効率的にデータ連携できる体制などが求められます。特に、実際の現場での労働状況をリアルタイムに反映し、自動分析・レポート化できる機能もあると、派遣元企業との連携・報告体制が一層強固になります。
モバイル対応機能
派遣社員は、派遣元企業から派遣先企業へ出向いて勤務する形態、つまり常時リモート体制で勤務しているとらえることもできます。そのため、外出先や複数の勤務地からでも簡単に打刻できるモバイル対応は、現代の勤怠管理に不可欠といえます。出先のPC、手元のスマートフォンやアプリで容易かつ確実・安全に記録できる仕組みの有無、使い勝手を確認しましょう。
おすすめテレワークに有効な勤怠管理方法|効率的な手段と導入のポイント
申請ワークフロー機能
残業申請や休暇申請をオンラインで完結できるワークフロー機能もニーズの高い機能です。派遣社員にとっても上長にとっても、また、それぞれの社にとっても大幅な手間削減につながります。承認フローが自動化されることで、申請書類の紛失や承認の遅延を防ぎ、正確な勤怠管理が加速します。
データ連携機能
データ連携機能/データのインポート・エクスポート機能/API連携機能は、派遣元企業と派遣先企業との間で正確かつ効率的な情報共有に向けた重要機能です。
勤怠情報のデータは、派遣先企業では派遣社員の実際の勤務時間・状況を把握し、管理するためにが必要です。派遣元企業も同様に、勤務状況の把握と法順守の観点も含めた管理、給与計算や労働時間の管理に使用されます。
勤怠管理システムへこのニーズに適したデータ連携機能があることで、正確な労働時間管理、給与計算管理、法順守カ観点の管理を実現し、双方の企業にとって効率的な運用が可能になります。また、相手とデータ連携するために必要となる技術的な協議もスムーズに進むでしょう。
おすすめAPI連携機能でできること
派遣社員の勤怠管理に向けたおすすめ勤怠管理システム11選
派遣社員の勤怠管理における上記のニーズを踏まえ、基本機能とともに「ワークフロー機能」「データのインポート/エクスポート機能」「労働時間レポート機能」を備え、「できるだけ早く/できるだけ安価に」を実現するクラウド/SaaS型のおすすめ勤怠管理システムを紹介します。(製品名 abcあいうえお順/2025年2月時点)
関連IT製品の無料プラン/無料トライアルはなぜ無料なのか、どこまで無料で使えるのか