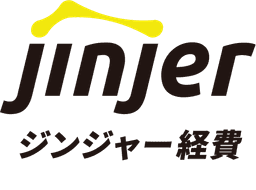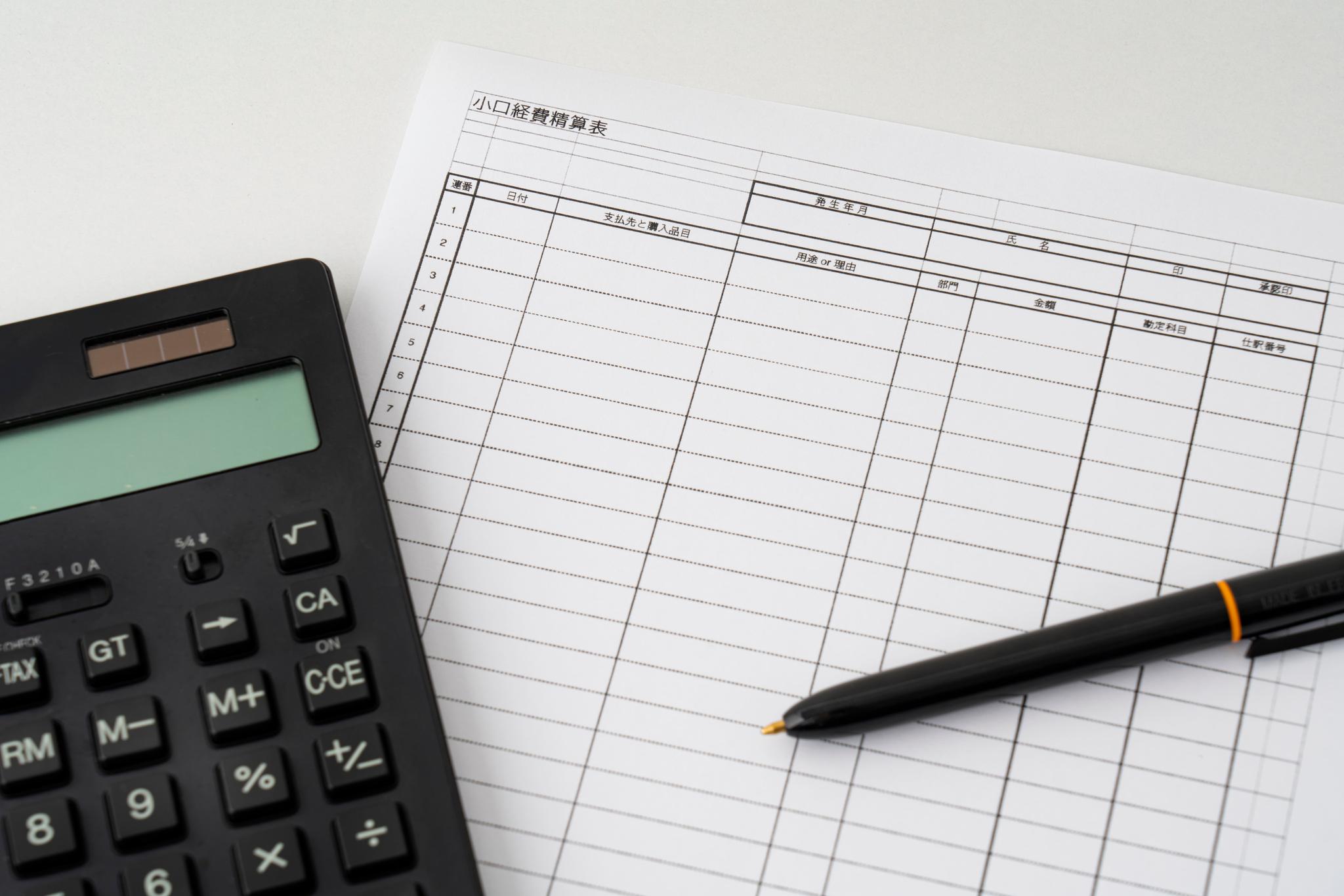(画像:写真AC)
経費精算のプロセスに課題を抱えている人へ。改正電帳法の施行に沿い、各企業で帳票・請求書類の電子化/電子データ保存におけるプロセスやルール策定・対策が進み、整備されるようになっています。しかし「従業員(内部)向け対策は後回し/これから」という声も聞かれます。
この記事では“これから”の企業もスムーズに対応できるよう、電子帳簿保存法の順守を踏まえて従業員立替経費精算に関わる領収書・レシートへの対応方法を整理し、法令順守と業務効率化を両立する課題解決のポイントを分かりやすく解説します。併せて、いくつもの課題をスッと容易に解決するおすすめの経費精算システムをご紹介します。
目次
従業員立替経費精算の領収書やレシートも電子帳簿保存法の対象
電子帳簿保存法(電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成10年法律第25号/2022年1月1日施行))は、経済社会のデジタル化を踏まえ、経理の電子化による生産性の向上、記帳水準の向上を目的にする法律です。2022年1月の改正で、電子データとしての定義と扱い方、帳簿類を電子的に保存する際のルールが抜本的に見直され、一部要件も緩和されました。
電子帳簿保存法における電子データ保存要件は「電子帳簿等保存」「電子取引」「スキャナ保存」の3区分に分かれています。各税法でこれまで“紙での保存”が義務付けられていた帳簿類を「電子データとして保存」できるよう緩和し、併せて電子データとして「取引情報の保存義務」のルールなどを定めています。詳しくは「改正電子帳簿保存法とは? 電子取引の電子データ保存とは?」を参照ください。
では従業員が立て替える経費はどうでしょう。多くは受けとった紙の領収書やレシートを持って、会社へ申請して処理します。この「紙の領収書やレシート」も電子的に管理するには、電子帳簿保存法の要件に合わせて適切に保存する必要があります。電子化すれば紙保管の手間やコストを削減できる反面、タイムスタンプの利用や可視性の確保など、特有のポイントを押さえなくてはなりません。
電子帳簿保存法の保存区分
電子帳簿保存法は保存方法や対象書類に応じて大きく3つの区分に分かれています。何はどの区分に該当するのか、どのように電子データとして保存するのかについて改めて確認しておきましょう。
- 電子帳簿等保存
- 電子取引データ保存
- スキャナ保存
電子帳簿等保存
電子データで作成された帳簿そのものを保存する区分です。端的には、経費精算システムや会計ソフトなどを使って作成した「データそのもの」が対象です。具体的には、会計ソフトで作成した仕訳帳データ、システムで作成した請求書ファイルなどが対象で、それらをそのまま保存・保管し管理するイメージになります。保存義務を満たすためには、訂正や削除があった場合の履歴管理やシステム操作ログなどの要素が求められます。
電子取引データ保存
メールやWeb、取引先システムなどから受領する注文書、契約書、請求書、見積書、領収書などの電子データが対象です。2024年1月から「やりとりしたものが電子データならば、電子データのままで保存する」とルール化され、データを“印刷して紙で保存する”は認められなくなりました。電子データのままタイムスタンプなどの要件を満たして保管する必要があります。
経費精算・従業員立替払いのフローにおいても、例は少ないかもしれませんが「取引先からPDFでレシートや領収書が送られてきた」などの場合はこの区分に該当します。
スキャナ保存
決算関係書類以外の、取引先などから受領した紙の請求書、購買で受領した領収書やレシートが主に該当します。これらの紙を紙のまま保存する代わりに、スキャンして「電子データ化したもので保存する」ことを認める区分です。
具体的には、紙の領収書屋レシートをオフィスのスキャナー機器・コピー複合機でデータ化する、あるいはもっと簡単に「スマホのカメラで撮って残す」ことで電子データになります。
ただしスキャナ保存には細かな要件、最低解像度や階調(原則はカラー画像で)などもいくつか定められています。
おすすめ「電子帳簿保存法」の対応方法 まだ間に合う? 帳票電子化の気になる疑問、対策手段を分かりやすく解説
立替経費精算の領収書・レシートの保存方法
従業員が出張費や交際費などを立て替えて支払った際に受け取る紙の領収書やレシートは、スキャナ保存制度や電子取引に該当する形で運用することが求められます。電子データとして保管するメリットは大きいです。しかし、法要件に沿って処理・管理されていないと税務調査時などに対応できなくなる可能性があります。
これらを手軽にかつ確実に解決するには、各種要件に沿ってあらかじめその機能が設計されている「経費精算システム」を用いることが近道です。スマホで領収書を撮影し、その画像データへ法的要件を満たす情報や対策を付加して電子データ保存する体制が整います。
無料でIT製品選びをお手伝いします
領収書・レシートを電子データで保存するメリット
経費精算における「紙」の取り扱いは、いまや手間とコスト面で無視できない課題です。電子データでの保存はこうした課題をまとめて解決できます。
- 管理・保管コストを削減できる
- 検索・アクセスが容易になる
- 会計業務の負担が軽減する
- 経費精算の透明性を向上できる
管理・保管コストを削減できる
端的に大量の「紙」をファイリングし、物理的に長年保管するには、かなりのスペースと面倒な管理作業が必要です。電子データならばこの課題を一気に解消できます。
また、自社・取引先各社で電子化が進めば郵送書類なども削減されていきます。書類取り扱いに関する物的コスト、人的負担も軽減されるでしょう。
検索・アクセスが容易になる
データ化されていれば「検索」が極めて簡単になります。サッと検索するだけで目的の書類・情報を瞬時に見つけ出し、簡単にアクセスできるようになります。
想像するまでもなく、経費精算の確認作業や監査対応がスピードアップします。会社全体で統一的にデータ管理を行えば、担当者同士の情報共有も促進し、ミスや重複申請のリスクを減らす効果も期待できます。
会計等業務の負担が大きく軽減する
データ化されていれば、自動仕訳や会計システム/ソフトとの連携もスムーズになります。経理担当者の入力作業を減らし、また人力作業に由来するミスやトラブルが起こる可能性も大きく下げられ、確認・修正の手間全般を大幅に軽減できます。
経費精算の透明性を向上できる
電子データでのやり取りは、不正や改ざんを防ぐ効果も期待できます。何か不正を企てたとしても痕跡が残りやすく、システムによってアクセス履歴や利用者権限と制御、変更履歴のようなデータ管理も比較的容易です。また、監査時にも書類をスムーズに提示できるため、透明性の高い経費精算フローでコンプライアンス意識も高めたい企業にとっても大きなメリットがあります。
領収書・レシートを電子データ保存するときの注意点
スキャナ保存は「スマホで撮るだけ」のように手軽に扱えると感じられる半面、制度や電子取引の要件を理解しない/満たさないまま運用するのでは、税務調査など何らかで問題になるリスクが高まってしまいます。領収書の電子データ化運用における注意点は以下の通りです。
- スキャナ保存制度保存要件の理解
- データと紙の両方が提供された場合の対処
- データ化した紙の原本も一定期間保存することを推奨
スキャナ保存制度の保存要件
紙で受け取った領収書・レシートをスキャン保存する際には、一定の解像度(200dpi以上/原則としてカラー画像)を満たしたスキャン機器(複合機やスマホカメラ)で行い、原則として受領後速やかに取り込むことが求められます。また、データの真実性や可視性を担保するためにタイムスタンプを付与することが求められます。
また、法令における電子データには「真実性の確保」と「可視性の確保」の2つが重要な要件として求められます。真実性の確保には、タイムスタンプの付与や改ざん防止措置が必要で、入力責任者の明確化も求められます。可視性の確保には、保存するデータが容易に検索・閲覧できるよう、日付や金額、取引先などの属性情報を付与し、システム上で迅速に表示できるようにすることが求められます。
参考:国税庁「電子帳簿保存法が改正されました(令和3年5月/令和3年12月改定)」
データと紙の両方が提供された場合の対処
取引先によっては同一内容の電子データと紙の領収書を同時に発行してくる場合があるかもしれません。電子データか紙か、どちらを正本とするかの取り決めなどによって対応が分かれます。端的には、領収書は複数発行されないものなのでいずれか一方を選択します。正とするのが電子データならば電子データ保存区分に、紙ならばスキャナ保存の区分に沿って管理します。
どちらを正本として扱うかは取引先と取り決めを、今回のような内部向けならば社内規程やマニュアルで明確化しておくことも大切です。
参考:国税庁「電子帳簿保存法一問一答(令和6年6月)」
データ化した紙の原本も一定期間保存することを推奨
法的には、電子データ化した紙の領収書・レシートはすぐに破棄してしまって問題ありません。
しかし電子データの不備やトラブルが発生した場合に備え、必要に応じて正確な情報を確認・修正できる保障になるよう一定期間は保管しておくことも推奨されます。要不要を含め、会社としてルール化しておくとよいでしょう。
「領収書自動読み取り機能」に強みを持つ経費精算システム6選
(製品名 abcあいうえお順/2025年2月時点)